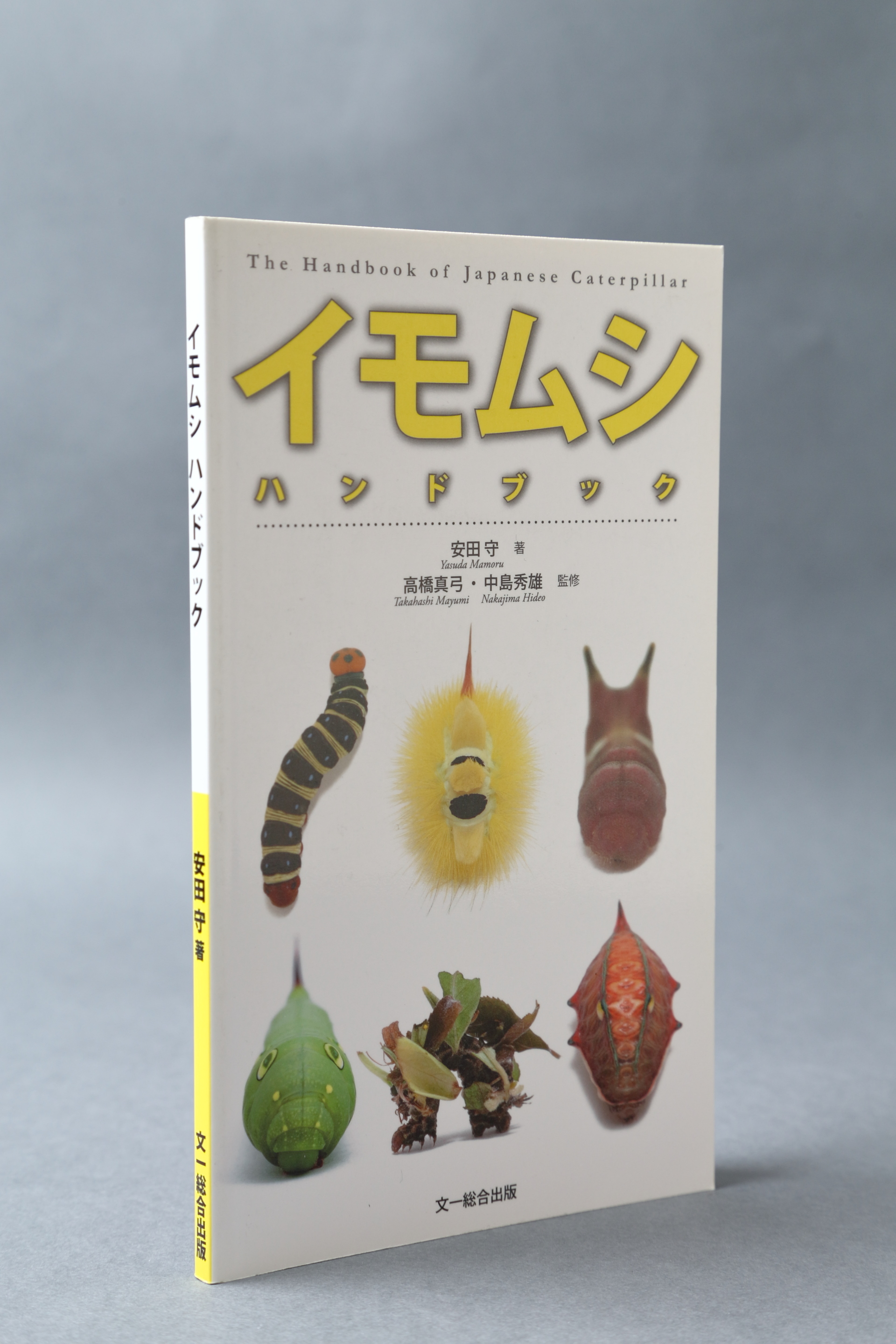「こんな物語を書きたい」。作家・柳美里が母子で読み返した『ダリアの帯』とは?
第3回「柳美里書店の10冊」
母子で繰り返し読んだ大島弓子

母がいちばん好きだったのは、大島弓子です。
「いちご物語」や「全て緑になる日まで」や「四月怪談」や「バナナブレッドのプディング」や「桜時間」が収録された単行本は本の形が崩れるまで、母子で読み返しました。
はじめて『綿の国星』を読んだのは、中学一年の夏休みだった、と記憶しています。社会はバブルに向かって突き進み、同級生たちは「いい大学に入って、いい会社に入って、玉の輿に乗る」と言って憚りませんでした。
そんな中、自分が自分以外の全てと軋んでいるように感じていたわたしは、捨て猫として登場したチビ猫が、人間になることを願いながら、ラフィエルという美しい銀猫によって「猫は人間になれない」と言い渡されて願いを挫かれる『綿の国星』に魅かれたのでした。
そう、大島弓子は、挫折と喪失を繰り返し描いてきた漫画家です。
「ダリアの帯」は、今でもときどき読みます。黄菜<きいな>は18歳の時に4歳上の一郎と恋に落ち、まだ若過ぎる、という双方の家からの反対を押し切って、好きだという衝動だけで結婚に踏み切る。
三年後のある日、黄菜は掃除機かけをしている最中に階段から転落し、流産する。
病院に駆け付けた一郎に、「赤んぼうがいたなんて知らなかったの」と黄菜は傷付いたレコードのように繰り返す。
「事故だったんだから しかたないよ また生めばいいよ」と声をかけた一郎に、黄菜は水の入ったコップを投げつける。
黄菜の日常は崩れて行く。全ての家事を放棄し、会社に出掛ける一郎のワイシャツの背中に「一郎君をとらないで」と書く。
一郎は、会社の同僚である雪子嬢への恋心を見透かされた、と思う。
黄菜の精神はさらに壊れ、様子を見に訪れた母親を「鬼だ」と罵り、子供を流産したのは自分の意志であり、母親の血を受け継がせたくなかったからだ、と責め立てる。
深く傷付いた母親は「あの子をよろしくおねがいします」と一郎に頼んで立ち去る。
一郎は「ぼくの結婚は失敗した」と思う。――とあらすじを書くと、陰惨な純文学のような作品だと思われそうですが、違うのです。黄菜は孤独の極みの中で現実の軸から外れて幻想へと浮かび上がり、一郎の手を取ってふんわりとおしまいに着地するのです。
黄菜の喪失と、一郎の挫折を真綿のようにくるむのは、死です。
胎児の死という内側の喪失を通して、開かれた外側の愛に押し出される、と言ってもいいかもしれません。
「ダリアの帯」を読んだ17歳のわたしは、「こんな物語を書けたらいいな」と思ったのです。
- 1
- 2